作品紹介BLOOD+
- 各話紹介
- 第1話「ファーストキス」
- 第2話「魔法の言葉」
- 第3話「はじまりの場所」
- 第4話「アブない少年」
- 第5話「暗い森の向こうへ」
- 第6話「おとうさんの手」
- 第7話「私がやらなきゃ」
- 第8話「ファントム・オブ・ザ・スクール」
- 第9話「それぞれの虹」
- 第10話「あなたに会いたい」
- 第11話「ダンスのあとで」
- 第12話「白い霧にさそわれて」
- 第13話「ジャングル・パラダイス」
- 第14話「さいごの日曜日」
- 第15話「おいかけたいの!」
- 第16話「シベリアン・エクスプレス」
- 第17話「約束おぼえてる?」
- 第18話「エカテリンブルグの月」
- 第19話「折れたココロ」
- 第20話「シュヴァリエ」
- 第21話「すっぱいブドウ」
- 第22話「動物園」
- 第23話「ふたりのシュヴァリエ」
- 第24話「軽やかなる歌声」
- 第25話「赤い盾」
- 第26話「サヤに従うもの」
- 第27話「パリ・ジュテーム」
- 第28話「限りあるもの」
- 第29話「呪われた血」
- 第30話「ジョエルの日記」
- 第31話「壊れゆく盾」
- 第32話「ボーイ・ミーツ・ガール」
- 第33話「信じるチカラ」
- 第34話「俺たちのいる世界」
- 第35話「希望のない明日」
- 第36話「すれちがう想い」
- 第37話「狂おしいまでに」
- 第38話「決戦の島」
- 第39話「魔法の言葉をもう一度」
- 第41話「私の居場所」
- 第40話「シュヴァリエの見る夢」
- 第42話「響く、歌声」
- 第43話「こころ乱れて」
- 第44話「光の中に」
- 第45話「手のひらを太陽に」
- 第46話「あした天気になあれ」
- 第47話「全ての血を超えて」
- 第48話「摩天楼オペラ」
- 第49話「二人の女王」
- 第50話「ナンクルナイサ」
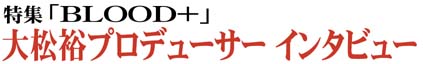
PROFILE
- 名前
- 大松裕(おおまつ・ゆたか)
- 経歴
- 1975年5月21日生まれ。兵庫県出身。
『BLOOD+』のプロデューサー。
プロダクション I.Gでは『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』のように制作担当として作品に関わるほか、『お伽草子』や『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』では脚本も手がけている。千葉ロッテマリーンズのファン。
魅力のあるフィルムは魅力のある現場からしか生まれない
——はじめに今回『BLOOD+』のご担当になった経緯を教えてください。
記憶がちょっとあいまいなんですが、たしか石川社長からいきなり焼肉屋に呼ばれたんですよ。一緒に呼ばれた藤咲(淳一)監督と店に入ると、アニプレックスの落越(友則)プロデューサーがいて、そこではじめて『BLOOD+』の話を聞いたんです。それがおそらく去年の10月頃のことでした。
そこから藤咲監督がプロットを練って、2週間後くらいには毎日放送の竹田(青磁)さんとお会いしてっていう流れだったと思います。そして、みんなで集まって全体のプロットを練り始めていきました。やっぱりオリジナル作品ということで準備期間に余裕を持つべく、早めにスタートしたんだと思います。
——プロデューサーとしての大松さんの役割とは?
一言で言ってしまえば“調整役”ですね。スタッフを集めたり、誰にどんなことをやってもらうかを決めたりといったスタッフリングが主な仕事です。
——『BLOOD+』の現場はどんな雰囲気ですか?
和気あいあいとしている時もあれば、一触即発な場面もありますよ。僕としては基本的にバランスが大事だと思っています。それから、緊張感は常に持っていられる関係でいなければならないとも思います。これから、スタジオ内の場所を移動して同じ場所にいるスタッフが増えていく中でどういう雰囲気を作っていくのかというところも僕の担う仕事のひとつだと考えています。
いつも、しかめっ面や眉をひそめた顔でモノを作っているというだけの現場にはしたくないので、いい空気が流れる場所にしたいなぁと思います。魅力のあるフィルムは魅力のある現場からしか生まれないと思いますからね。
——では、『BLOOD+』班の組織作りはどんな経緯で進められたのでしょうか?
藤咲が監督ということは決まっていたので、そこから先をどうするかっていう話ですよね。まずは、監督としての実務経験のない藤咲のサポートが必要だろうということで、僕がずっと『攻殻機動隊』で一緒にやっていた松本(淳)にいちばん最初に声をかけて演出チーフをやってもらうことになりました。
はじめは他の作品があるからって断られたのを何とかお願いしつづけてやって頂けることになったんです。 その次はデザインですね。やっぱりデザインというのは作品の方向性に直結すると思うので、それをきちんと決めなければいけない、と思っていました。
そこで、いろいろな紆余曲折がありましたね。劇場版の『BLOOD THE LAST VAMPIRE』の寺田(克也)さんの絵はすごく魅力的なんですが、50本のTVシリーズで考えると制作的に勝機を見出せなかった。だから、どうしても変えたいなぁと思ったんですね。ゼロから作り出したかった。
それで、まぁ最初はアニメーターのオリジナルデザインで行こうかな、と考えたこともあったんですよ。実際にI.Gの外から招へいして、アイデアを練った時期もあったんですけど、それもあまり上手くいかなかったり……。それじゃあ、寺田さんのイラストに戻そうという意見もあったり……。
デザインを決めている時に僕が一番考えていた事は、現場のスタッフのモチベーションを上げるデザインにしたいと言う事だったんです。つまりそれは、描きたいデザインを提供するっていうことです。もちろんそこには描きやすさも含まれます。特に今回は1年間続くTVシリーズですから、描きやすさや親しみやすさを持つデザイン、そしてスタッフが気に入ってくれるだろうデザインを何とか作り出したかったんです。そんなことを考えていたときに別の畑のキャラクターデザイナーをあたった方がいいのではないかという結論に至って、ネットで探しはじめたんですよ(笑)。
——ネットで探されたりするんですか?
はい。フリーのイラストレーターを中心に探していて目星をつけていた中に、箸井(地図)さんもいたんです。箸井さんに一回声をかけてみようと思ったんですが、その頃は大阪にいらしたんですね。ただタイミングの良いことに角川書店の少年エースという漫画雑誌に箸井さんの連載があって、1月に角川書店のパーティに出席するために上京してきた箸井さんに直接お会いできたんです。
そこで、お話してみたら偶然なことに箸井さんも、I.G作品がすごく好きだったっていう……。その時はすごく縁というものを感じてこの人でいくしかないと思いました。そこからいくつか描いてもらって、いろんな方々にも見ていただいて、GOサインが出たという感じですね。
結果的に見て、箸井デザインがすごくいいと思うのは、まず現場のスタッフのウケがいいんですよ。これは男女を問わず反応がいいんです。そこは成功したと思っていますね。一般の方にウケるデザインって一口に言っても雲をつかむような話じゃないですか。こういうデザインだから絶対にウケるっていうのは、実のところ結果論でしかないと思っているんですよ。
放映に向けて準備している今のような段階で、このデザインは確実にウケるという確信は、正直持てない部分もありますからね。ただ、スタッフが気に入ってくれているっていうところは大きいので箸井デザインの起用は僕の中では大成功ですね。
I.Gブランド的な部分をいったん解体したい
——箸井さんのデザインはどのくらいの範囲にわたるものですか?
キャラクターに関して、ほぼ全般にわたっています。熱心にやっていただいてますし、箸井さん独特のあったかさがキャラクターから伝わってきますね。それに打ち合わせを重ねる事にどんどん良くなってきていると思います。最近上げてもらったサブキャラクターなんかも見るだけでイメージを湧かせてくれるようなものが出てきていますしね。
今は大阪から東京に出てきてくださったので、適度にコミュニケーションをとりながら作業が進められていて、箸井さんのやる気というかパワーがいい意味で『BLOOD+』という作品に影響してくれていると思いますよ。
ただ、箸井さんはもともと漫画家でいらっしゃるので、描いていただいたデザインをそのままアニメのデザインとして使うのはちょっと難しいんですよね。それで、アニメのデザインとして使いやすいようにリライトする役割が必要だったので、I.Gの中でいちばんキャッチーな絵が描ける石井(明治)に現場とのパイプ役をお願いしたんです。
彼は実力はもちろん、真面目で数をこなせるので適役でした。総作画監督として全ての話数のほぼ全カットに絵を入れてもらっていますし、絵のキーマンになると思います。キャリアもネームバリューもある方なので安心してお任せしていますね。
——『BLOOD+』をつくる上で劇場版『BLOOD THE LAST VAMPIRE』を意識したところは?
I.G作品のある種I.Gブランド的な部分をいったん解体したい、という気持ちはありました。I.Gが世に送り出した良い作品はたくさんあるんですが、やっぱりキャラクターを獲得していないという思いが僕の中にあったんですね。それは挑戦してみたいところだし、僕自身のテーマとしても“キャラクターを獲得する”というのが大きかったんですね。
業界内でも“BLOOD”って言うと「えぇっ!」と一歩引かれてしまう反応が多かったんですけど、デザインを見せてみると「こういう方向でいくのか…」とさらにまたさんざんビックリされたりしましたけどね。でも、逆に言ってしまえばこういう方向性で割り切らないと1年間のTVシリーズとしてもたないと思うし、オリジナルを作る意味もないんじゃないかと思うんですよ。
もちろん劇場版の『BLOOD THE LAST VAMPIRE』があってこその『BLOOD+』なんですけど、やはり劇場版をいったん解体して再構築することは良かったというか、そうせざるを得なかったという部分が僕にはあったんです。結果的にいい方向になっていると思っていますよ。
——『BLOOD+』の小夜はショートカットで、劇場版の小夜の象徴的なおさげ髪とはまったく違いますよね
現代を舞台にするとした時に、劇場版の小夜のようなセーラー服におさげ髪はないとは思っていました。あの小夜のビジュアルは一芸だと思っていて、そう何度もひっぱってこれるような代物ではないと思うんですよね。だから、今の時代に合ったデザインに一新しよう、と。
石川社長からはロングヘアーの方がいいんじゃないかと言われたりもしたんですけど、絵として動かしやすいことや活動的なイメージにも合うところから、あの小夜のデザインに決まりました。あとは、ショートヘアーをどういうシルエットにするかというところでは、けっこうアイデアを出しあって詰めていきました。
魅力的なキャラクターをしっかりしたドラマで描いていく
——小夜を取り巻くキャラクターたちの存在とは?
ハジやカイという男性キャラクターたちをいかに魅力的にするかは大事だと考えています。去年の年末にあった『鋼の錬金術師』のイベント(「鋼の錬金術師FESTIVAL-Tales of another もうひとつの物語」)や7月30日に行われた大阪でのイベント(「MBS ANIME FES.’05~大阪城エクスペリメント 真夏の夜の夢~」)に行ってみて思ったんですけど、中高生の女の子たちのパワーがすごいんですよね。
特にあの放送枠だからなのかもしれないですけど、女子中高生という層は無視できないなというのは、すごく実感しました。大阪のイベントでは『鋼の錬金術師』や『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』のキャラクターが出てくるだけで、「きゃーっ!」という大歓声が上がる。すごいなぁっていうのが正直な感想で、こういうファンの反応を生で見られたことは大きかったですね。もちろん、イベント会場に足を運ばない層の視聴者の方もたくさんいるんでしょうけど。
『BLOOD+』もそこまで行かなければいけないなと思いました。今回の放送枠で女の子が主人公なのは『BLOOD+』だけなんですよ。そういう面ではリスクが高いんじゃないかと言われたこともあるんです。確かにあのマーケットを対象にするんであれば、女の子が主人公ということは致命的になりかねないという見方もできますしね。でも、主人公は小夜で、これは変えられないわけだからどうすべきか、となったんです。
そうなると、小夜の周りの男性キャラクターを魅力的に描いていくしかないと。ただ、あまり狙いすぎはよくないとは思っていますけど……。魅力的なキャラクターをしっかりしたドラマで描いていく、まあ当たり前の事なんですけど、それができればどんな層のお客さんにも胸を張って観せれるものなるはずですからね。
——小夜はやっぱり女の子なんですね? ヴァンパイアの血を引くということで性別をあいまいにするという選択肢もあったと思うのですが……
そういう方法もあったかもしれないですね。ただ、最初のうちから脚本とかの部分で少女漫画をすごく意識していたところがあったんですよ。それと、やっぱり絵コンテがあがってきた時の印象が小夜はとても“女の子”していたんですね。演出の松本からのそういうアプローチを受けて、小夜は女の子だとはっきり認識しました。小夜が女の子であるというのはこの作品の隠れテーマでもありますし、女子高校生であるという面から学園ドラマ風な展開もアリだと思いますしね。
作品を動かす力として大事なもの
——大阪でのイベントはいかがでしたか?
サンライズやBONESといった他のアニメーション製作会社も関わっていたので、個人的には普段あまり会うことのない同業者にいろいろと話を聞けたことが大きかったですね。いい刺激もいっぱい受けられたと思います。
あとは他の作品が会場に流れて、それに対するお客さんたちのレスポンスを生で見てみて、ちょっとした危機感も感じました。こういう影響力のある作品に『BLOOD+』を育てていかなければならないなぁと強く感じたんですね。
イベントの後の打ち上げでも脚本陣を交えていろいろと話をして、あらためて気を引き締めました。実のところ、こういうイベントは参加するアニメーション製作会社としては直接的な経済利益を生む場ではないんですよ。だけど、やる価値はすごく大きいんだということを感じました。業界全体が盛り上がっているんだという雰囲気だったりとか、作品ファンの反応を生で吸収できることだったりとか、作品を動かす力として大事なものがたくさんありましたね。
あとは個人的に大切にしていることとして“一体感”というのがあって、これは現場だけじゃなくて宣伝やってくれる人とか音楽を担当してくれる人とか、いろいろな形で関わっている人すべてをひっくるめてひとつのチームと言う事強く感じていたいということなんですね。
今回のイベントの時に『BLOOD+』のブロックがあって、やっぱりそこに登場してくるチェロ奏者の日野俊介さんや、最後にかっこよく締めくくってくれた主題歌の高橋瞳さんとかを見ていて同じチームの一員なんだという意識がさらに強くなったんですよね。こういう大きな一体感を感じられたのは大変良い収穫でした。
——音楽の話が出ましたが、そのあたりでの関わりは?
音楽に関しては基本的にソニーミュージックにお願いしています。あの枠の傾向として1クールごとに楽曲が変わるので、一年のTVシリーズでOP、ED合わせて8回ですよね。僕の持っていたイメージとしてタイアップ曲は機械的に決まっていくものかと思っていたんですが、実際は全然そんなことはなかったです。
こちらが持っている作品の世界観や目指しているものをきちんと聞いてくれて、それを踏まえた上で曲を作ってくれているんだなって思いました。そういう風に気づいてから『鋼の錬金術師』の主題歌を聞きなおしてみたんですけど、やっぱりどれも『鋼の錬金術師』の世界観とちゃんとリンクしている歌なんですよね。
そうやって作品のために音楽を作っていただけるのはやっぱり嬉しいですね。『BLOOD+』に関してもこちらが考えている大まかな作品のコンセプトだったり、小夜の背負っている運命なんかを時間にすると2時間程度でお伝えしました。それで、出来あがってくる歌詞を見ると「なるほど」と思う部分や納得できる部分がたくさんあって、作品を大事にしながら音楽を作って頂いているいう感じがしますね。
—— 劇伴(BGM)もソニーミュージックが担当を?
劇伴はアニプレックスの尽力によりマーク・マンシーナ(Mark Mancina)が担当し、音楽プロデュースにハンス・ジマー(Hans Zimmer)が参加してくれています。これは藤咲監督も僕も決まるまで知らされていなかったので、聞かされた時にはかなり驚きました。
すでに何曲か出来上がって送られてきているんですけど、最初に聞いた時は「これ、どこで使うのかなぁ?」というのが正直な感想でした(笑)。どれもハリウッドの大作映画に使われるような重厚な音楽なんですよ。とはいえ、実際に絵に音楽が乗ってみると、意外にピッタリ合ってしまったりすることは多いので、大丈夫だと思います。
日本人がどうしても知ることのできないこと
——作品の最初の舞台となる沖縄にはロケハンに行かれたそうですね?
最初に監督を含めて5人くらいのスタッフで行って設定として使う地域や雰囲気を取り込んで、2回目に行った時には美術設定に関わるスタッフなんかも連れてさらに細かい資料集めをしました。沖縄を舞台にするというのは竹田プロデューサーからの提案だったように思います。
今年はちょうど戦後60年の節目になりますし、沖縄には在日米軍の7割がいますから、きちんと自分の目でその現実を見ておきたかったんです。僕ははじめて沖縄に行ったんですけれど、米軍の存在が沖縄にとっていかに大きいかということを実感しましたね。
それに、不謹慎かもしれませんが、やっぱりドラマの舞台としてはおもしろいなと思いました。一つの島に日本とアメリカというそれぞれ違った法律があって、日本人がどうしても知ることのできないこともいっぱいあるし、日本人と米兵と観光客が混在していて、しかも本土からの移住者の数も増えている、いろいろな顔を持っている土地ですからね。
そして、街の在り方がドラマチックなんですよ。今回は特に沖縄市のコザというところが舞台になるんですが、そこは昔はベトナム戦争の特需ですごく繁栄していたけれど、今は少しさびれた雰囲気があるんです。それでも、いまだに米兵向けと思われる店がいっぱいあるんですね。
どうしても米軍という存在に経済的な依存をせざるをえない感じとアメリカに対する何か恨み的な感情も感じられる、すごく特殊な環境なんですよね。フィリピンパブの印象がどうしても強く残っていて(笑)、実際に劇中にもそういう店が出てきます。沖縄のいろいろな部分をエンターテイメントとしての要素に使いながら、少しでも戦争によって残された問題を『BLOOD+』を見てくれる若い世代にも興味を持ってもらえるといいなぁと思っています。
——角川書店で3本のコミカライズ展開がすでにスタートしていますが、I.Gとしてはどのくらい関わっていますか?
けっこう関わっていますよ。内容はオリジナルですから、作品の概要とかどういうイメージで物語を作っているかとかお話ししました。漫画家の方とちゃんと仕事をさせてもらうのがはじめてだったので、すごく新鮮な部分がたくさんありましたね。
それぞれの作家さんが独自の世界観を持っていて、おもしろいと思いましたよ。僕の中では基本的には細かい設定とかを常に全部合わせてほしいというような希望は持っていなくて、作品の方向性さえ間違っていなければそれぞれの味を出してくれて最終的におもしろいものができればいいと思っているんです。
そういう意味でいうと少年エースの桂明日香さん、ビーンズエースのスエカネクミコさん、CIELの如月弘鷹さんという3人の持ち味がそれぞれよく出ていると思いますしね。そして、こちら側が学ばされることも多いですよ。みなさんキャラクターを作るのがとても上手で、こうやってキャラクターを立てていくんだっていう勉強になりますね。
プロットやネームを見せていただくんですが、基本的には自由にやっていただきたいので大きな修正をお願いすることはまずありません。小さな修正はいくつかお願いして2、3度やりとりするくらいでしょうか。3人ともすごく力のある方々だと常々感じています。
いろいろなところを旅していく物語
——毎日更新の制作日誌が公開されていますが?
5人で交代しながら平日は毎日更新していますね。これも竹田プロデューサーからの提案ではじまった企画なんですよ。『鋼の錬金術師』でも制作日誌を公開していて、「自分の誕生日のことを書いたりするとプレゼントが届いたりするらしいよ」と竹田さんから聞いて、「だったら、やってみようかな」なんていう軽い気持ちで引き受けたんですが、これがけっこう大変な作業なんです。
自分ひとりでは年に何回更新できるかわからないと思ったので、自分にもプレッシャーをかける意味で5人交代制にしてみました。週末が締め切りになっているんですが、僕以外の4人はけっこうちゃんと書いて送ってくるんですよ。僕は前日か当日にしかできてないですね(笑)。それに、僕以外の4人はどうもそれぞれのキャラが立ってきてるんですよね。僕だけフラフラしている感じがしているので、何とか軌道修正しなければならないなぁと感じています(笑)。
——I.Gにとって今回の『BLOOD+』という作品はどんな意味を持つ作品ですか?もしくは、終わってからどんな位置づけとなる作品を目指していますか?
これだけ注目される放送枠でTVシリーズをI.Gがやるというのは初めてで、劇場作品やOVA作品のイメージが大きかったI.Gが、会社としてこれからTVシリーズも増やしていく方向に転換していく最中の一本なんだと思っています。
その転換期の先駆けとなる作品に『BLOOD+』が位置づけられているという意識はすごく強いですね。いたるところで「I.Gは作品を見ている人間のことをちゃんと考えているのか?」というような質問をぶつけられることがあるんですよ。自分たちが思っている以上にそういうイメージを持たれているんだと認識させられたんです。
その反面支持してくれる人もたくさんいるとは思うんですが、今回は若い視聴者をどれだけ取り込めるかということに挑戦してみたいなと思っていますし、今のI.Gにとっても必要な挑戦だと思っています。それであまりいい結果を出せなかった場合は次に繋がらないのではないかという危機感は、余計なことかもしれませんが感じていますね。
僕としてはそうそう負け戦にはできないと思っているんです。50本のTVシリーズをスケジュールを崩さずにきっちりとこなして、まずはI.Gにも持久力があるというところを見せていきたいですね。あとは50本分のストーリーのボリューム感は経験もないので、どうしても手探りしながらの作業になるんですが、見ごたえのある作品にするべく今は全力で当たっています。
最終的にはいろんな人に評価されて、ビジネス的にもプラスになればいいなとは当然思っています。ですが、僕個人としては現場のスタッフに50本通してレベルアップができたとか良いアピールができたとかといった手ごたえを感じてもらいたいと思っているんですね。実際、依頼を受ける描き下ろしイラストの点数も今までに経験したことのない数になっています。今までそういう描き下ろしイラストに関わってこなかったスタッフにもチャンスはあると思うし、各クリエイターにはそういう機会をどんどん利用してもらいたいですね。
この作品を各クリエイターが自分のために仕事をする、利用していくというスタンスでやってくれて構わないと思っているんですよ。それで、その結果作品が良いものになればいいし、50本終わった時に各個人が手ごたえを掴んでくれていないと、たとえ商業的に成功していてもI.Gという会社としての連続性に繋がらない気がしているんですね。それが一番重要なことだと思っています。
——最後に放映開始を心待ちにしているファンに向けてのメッセージをお願いします
基本的にはいろいろなところを旅していく物語なんですね。見てくださる方々は主人公の小夜と同じくらいの年齢が多いと思いますが、キャラクターに自分を重ね合わせていろんな体験を追体験してもらって、エンターテイメント以外の部分でも何か感じ取っていただけるといいなと思っています。
あとは、いわゆるI.Gファンと言われる方々にはある種裏切らせてもらう形にはなるかと思いますけど、結果として見ればやっぱりI.G作品だったなと言われるような作品になると思いますね。デザインとかキャラクターの配置だけで判断せずに作品をちゃんと通して見てもらえれば、みなさんがI.Gに期待されているような要素は各所にちりばめられてますので、いろんな層に受け入れてもらえるような作品になっていると思います。いろんな先入観を捨てて、まず一度作品を見てみてください。よろしくお願いします。